第1章 Z世代が投資を「日常」にした時代
10年前、「投資」と聞けば特別な行為だった。
だが、2024年の新NISA開始を境に、20代の投資参加率は急上昇している。
マネーフォワードやSBI証券の統計によると、20代口座開設数は前年の約2倍に。
特に月1万円以下の積立層が急増している。
“お金の勉強”がYouTubeやTikTokで拡散され、「投資=自己管理」という認識が広がった。
つまり、Z世代にとっての投資は「ギャンブル」ではなく、生活設計の一部である。
第2章 SNSが作る“共感型マネー文化”
1. 投資系インフルエンサーの台頭
InstagramやXでは、若手の個人投資家がグラフやポートフォリオを公開する時代になった。
「資産報告」「NISA積立」「毎月の収益グラフ」などがバズの定番コンテンツになりつつある。
SNSはもはや情報媒体というより、“仲間意識”を作る場になっている。
「誰もが投資している」——その感覚が購買や行動を動かす。
2. 情報の多様化と“分散する信頼”
Z世代の特徴は、複数メディアから同時に情報を得ること。
ニュースサイトよりも「X・YouTube・LINEオープンチャット」で投資情報を得る割合が高い。
ただし、この多様性は情報の質に差を生み、誤情報も増えている。
その結果、「何を信じるか」よりも、「どう比べるか」が重要になっている。
第3章 インフレ時代の“守りの投資”へ
2020年代は、Z世代にとって初めての本格的インフレ環境となった。
物価上昇・円安・賃金上昇など、これまで「当たり前」でなかった経済状況を経験している。
- 「値上げニュース」=投資意識のスイッチ
- 「円安」=海外資産の必要性を理解
- 「副業・積立」=将来防衛の一手
“お金を動かす”ことが、もはや特別ではなくなった。
Z世代にとって投資は攻めではなく防衛であり、「生活を守るための仕組み」として受け入れられている。
第4章 積立投資の普及と「心理的ハードルの消失」
かつての投資は「元本割れが怖い」だった。
今のZ世代は「放置でいいならやってみよう」へと心理的ハードルが下がった。
要因は以下の通り。
- つみたてNISA・自動積立アプリの普及
- S&P500やオルカンなどの明確な定番化
- “他人の実績”を可視化できるSNS文化
また、積立を通じて「長期保有」が常識となり、
ブームの形も**“瞬間的な熱狂”から“継続的な文化”**へ変わりつつある。
第5章 Z世代が作る「次の投資常識」
- リスクを恐れずにシェアする文化 → 結果を公開し、成功も失敗も学びとして共有。
- 体験型の金融リテラシー → アプリ・SNS・学校教育で投資を「触る」経験へ。
- ドル資産・分散志向の定着 → 為替や米株への理解が自然な世代。
投資を“やるかやらないか”ではなく、“どう付き合うか”の時代が始まっている。
第6章 投資ブームの次の波へ
Z世代の投資行動には、「勢い」と「冷静さ」が共存している。
一方で、SNS上では誤情報・詐欺・過剰宣伝も増えており、
今後は“情報選別力”がリテラシーの中心になる。
次の投資ブームは、おそらくAI・円安・地政学といった要素を含む“構造的ブーム”になるだろう。
そこでも主役は、情報感度と実行力のあるZ世代である。
まとめ
- 投資ブームは「制度+SNS+世代交代」が重なった結果
- Z世代は“儲けるため”ではなく、“備えるため”に投資を始めている
- 今後は、投資が**「生活インフラ」化**する流れが加速する
ブームの波が去っても残るのは、「仕組みを理解した人」。
それが、次の10年を生きる世代の強さになる。
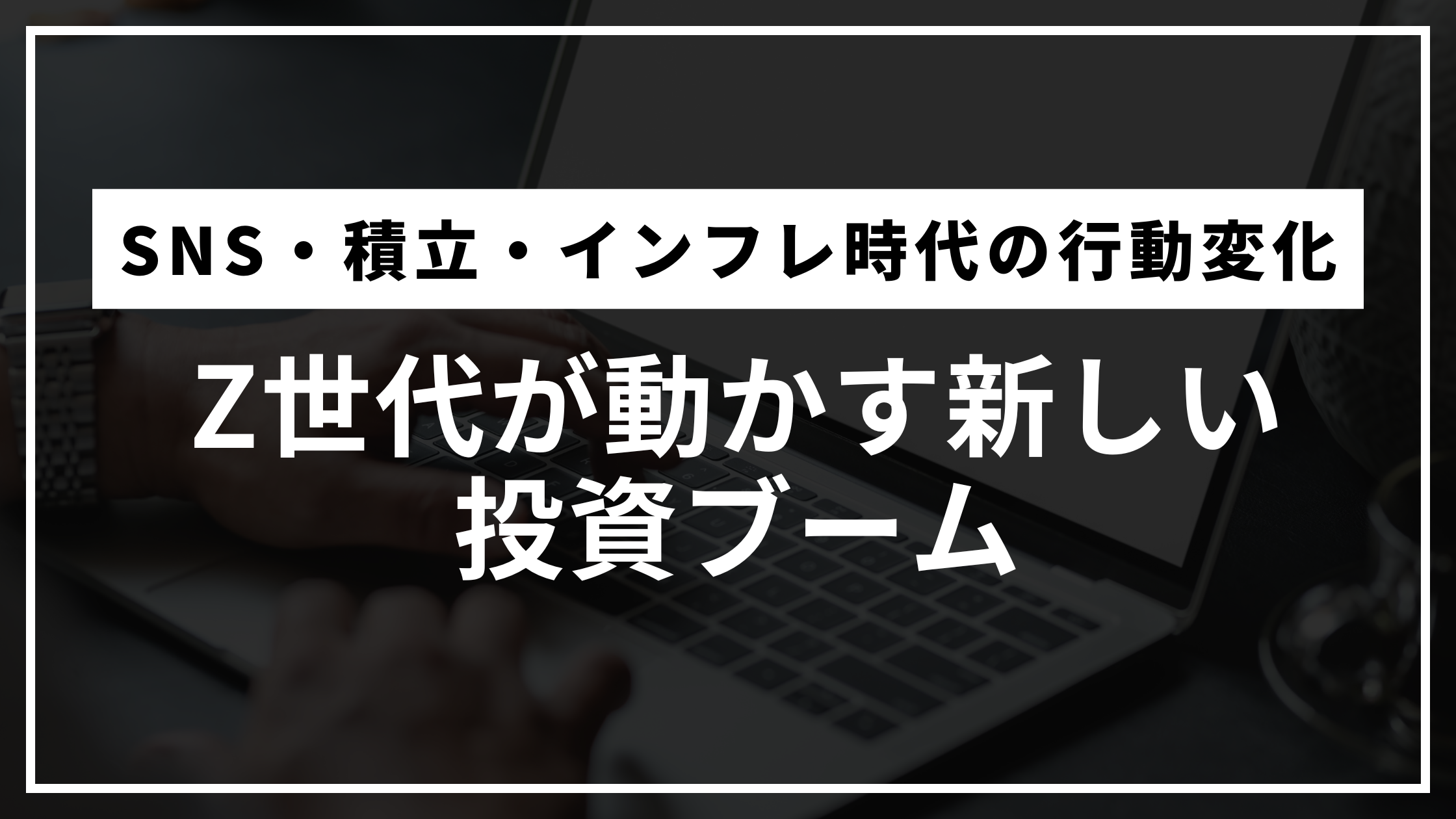
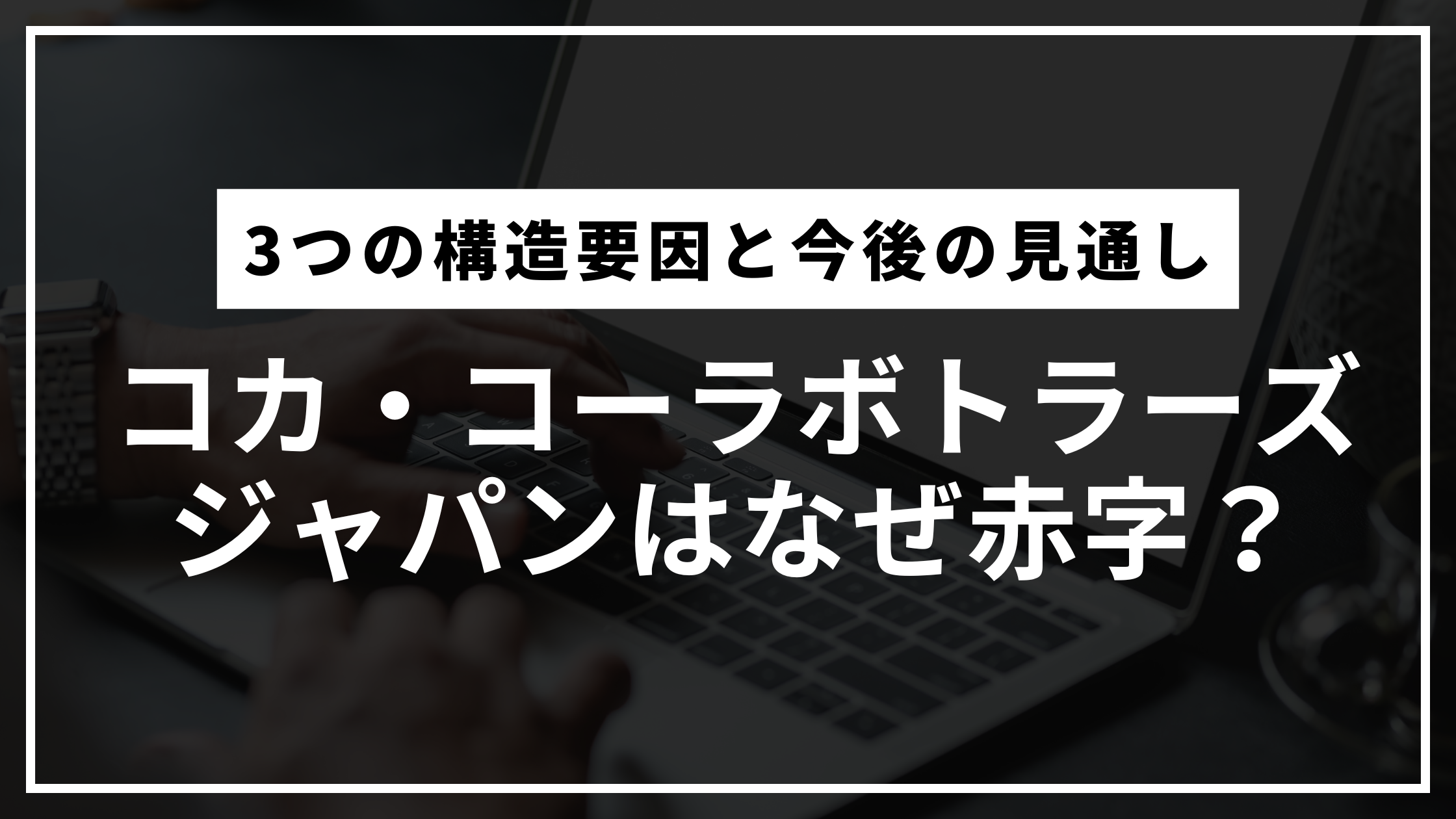
コメント