1. はじめに:旅行支出とライフスタイル
2025年8月から9月にかけて、名古屋・京都・横浜を訪れる旅行をしました。
交通費を含めた合計は 約17万円。これはあらかじめ想定していた範囲での出費であり、資産形成を崩さない計画的な支出です。
名古屋旅行では車を利用し、高速代を3人で割り勘することで費用を抑えられました。物を買うより経験にお金を使うことを重視しており、20代の今は「旅行や体験こそ積極的に投資したい分野」だと考えています。
次は10月に静岡旅行を予定しており、資産形成とライフスタイルの両立を目指して、出費にメリハリをつけることを意識しています。
2. 現在の総資産状況(2025年9月13日時点)
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 預金・現金・暗号資産 | 1,369,335 |
| 株式(現物) | 1,037,523 |
| 投資信託 | 6,388,843 |
| 債券 | 100,000 |
| ポイント | 82,935 |
| 総資産 | 8,978,636 |
| 負債(クレジットカード) | ▲351,202 |
| 純資産 | 8,627,434 |
総資産は 8,978,636円。
クレジットカード残高351,202円を差し引くと、純資産は 8,627,434円 となりました。
3. 株式の状況
株式は 1,037,523円で、総資産の約12%を占めています。
直近1か月間、S&P500は米国長期金利の上昇やインフレ再加速懸念を背景に下落する場面がありました。特に8月下旬から9月初旬にかけては、金利動向に敏感なハイテク株が売られ、指数全体も一時的に調整しました。
しかしその後は、米企業の堅調な決算や景気指標の底堅さが支えとなり、再び持ち直しています。株式部分は比率を低めに設定しているため、大きな下落局面でもポートフォリオ全体への影響は限定的でした。
むしろ「株式はリスクを取りつつも規模を抑える」という戦略が機能していると感じます。
4. 投資信託の状況
投資信託は 6,388,843円と、資産全体の約7割を占めています。
主力のS&P500連動ファンドは、直近1か月で上下動を繰り返しつつも全体的には底堅さを見せています。インフレ懸念や金利上昇の影響はあるものの、企業の利益成長や米経済の強さが評価され、結果的に投資信託全体の評価額は堅調に推移しました。
また、NASDAQ100連動ファンドはボラティリティが高く、一時的に大きめの下落も見られましたが、その後は買い戻しの動きが入りました。生成AI関連株やテクノロジー分野の成長期待が引き続き支えとなっており、長期的には成長エンジンとして期待できると考えています。
投資信託が全体の資産を牽引している現状を改めて確認でき、長期積立を続けることの重要性を実感しています。
5. 為替の影響
資産の多くがドル建てであるため、為替の影響は無視できません。
直近1か月は円安基調が続いており、資産評価額にはプラス要因となりました。特に1ドル=150円を超える局面では、ドル建て資産を保有するメリットが大きく感じられました。
ただし円高局面では逆に評価額が押し下げられるため、見かけ上の資産増減に振り回されないよう注意が必要です。円換算での数字だけでなく、ドルベースでも資産の増減を意識する視点を持ち続けたいと思います。
6. 負債の状況
クレジットカード残高は 351,202円。
このうち 10万円は9月の積立資金に充てられているため、消費による負債ではなく投資のサイクルの一部です。
つまり「借金」ではなく「一時的なキャッシュフロー上の負債」として扱っています。
残りの部分も計画的に返済可能な範囲に収まっており、資産形成のリスクにはなっていません。むしろ「投資と日常生活をどう管理するか」を意識するよい機会になっています。
7. 積み立て内容(2025年9月時点)
| 投資商品 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 62,000 | 米国大型株 |
| ニッセイNASDAQ100 | 20,000 | ハイテク中心 |
| eMAXIS Slim オールカントリー | 15,000 | 全世界株式 |
| eMAXIS Slim TOPIX | 3,000 | 日本株全体 |
| 合計 | 100,000 | 毎月積立額 |
毎月10万円をコツコツ積み立てる仕組みは変えず、長期での資産形成を継続する予定です。
8. 今後の注目点
- 米国市場の調整が一時的か、それとも長引くか
- 為替が円安基調を続けるか、反転して円高に向かうか
- 投資信託の堅調さが維持できるかどうか
- 旅行などの生活支出と投資をどう両立していくか
資産は確実に積み上がっていますが、「増やす」と「使う」の両立をどう実現するかが今後の課題です。
以上が、**2025年9月13日時点の総資産レポート(増量版)**です。
数字の裏にある生活や投資判断も記録しながら、1000万円の目標に向けて一歩ずつ進んでいきます。
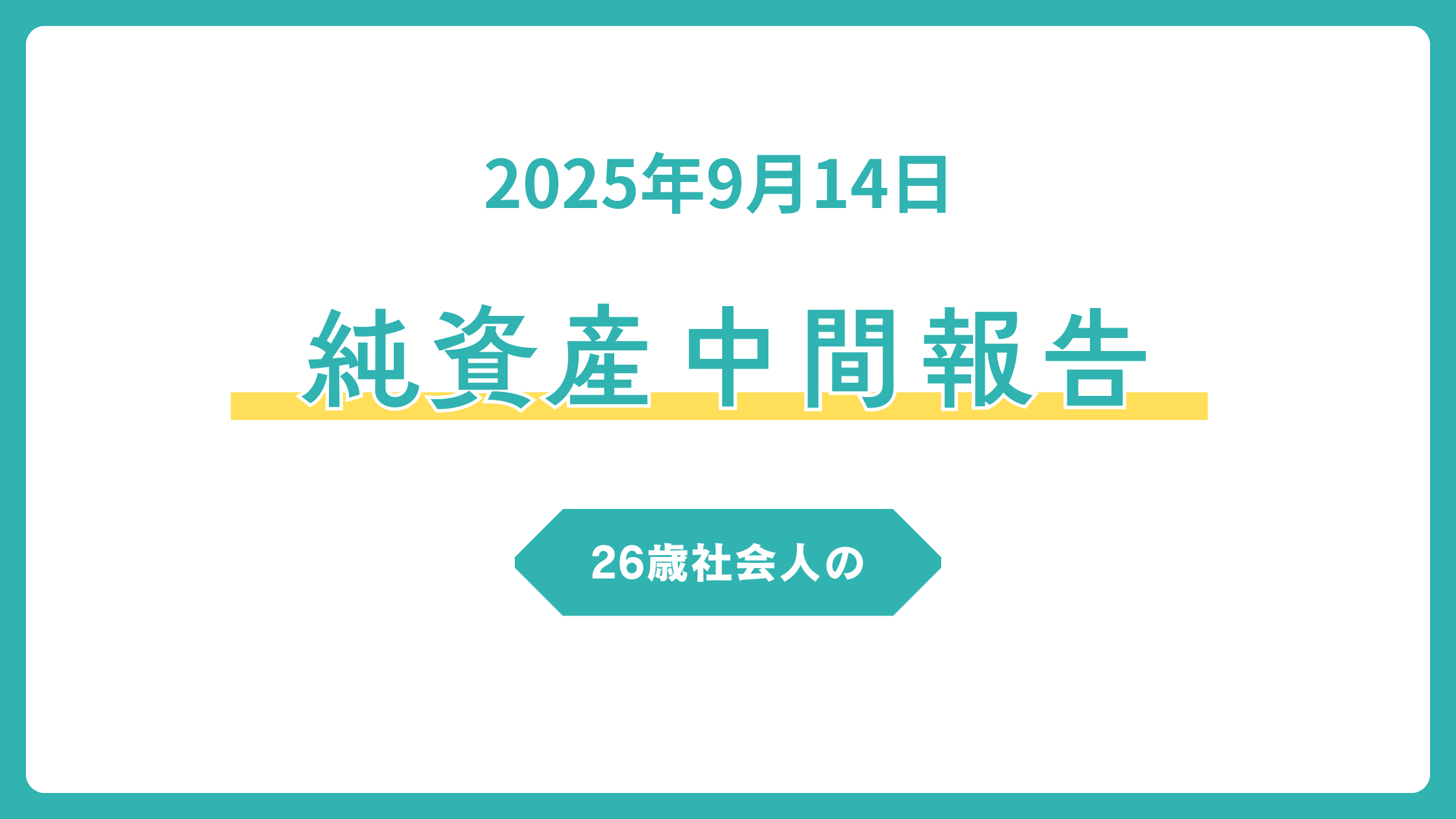

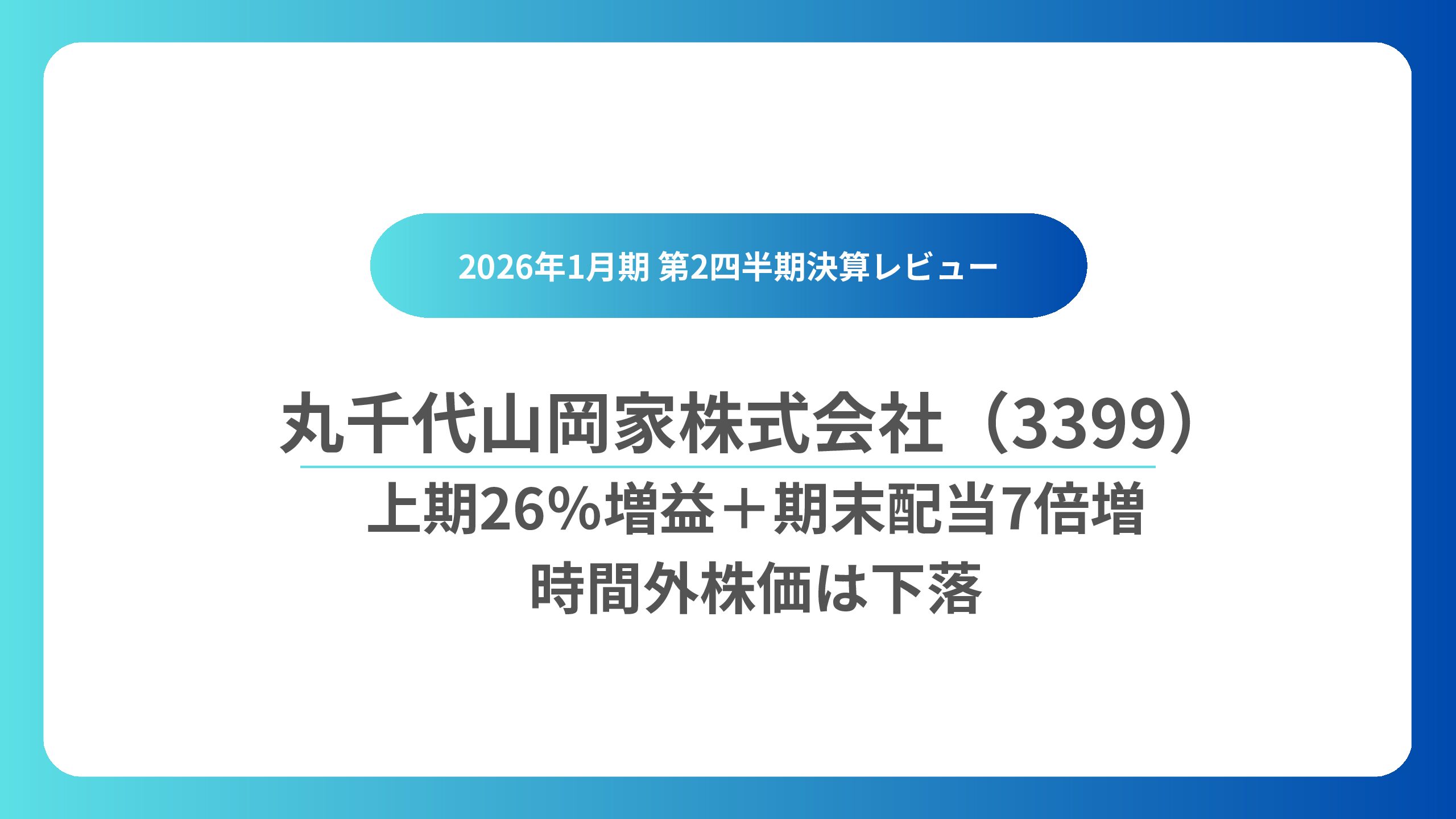
コメント