- はじめに
- 戦後復興と投資の始まり(1945〜1950年代)
- 高度経済成長と株式市場の拡大(1960〜70年代)
- 財テクと投資熱の高まり(1980年代前半)
- バブル経済と史上最大の投資ブーム(1985〜1989)
- バブル崩壊と「失われた10年」(1990年代前半)
- ITバブルと新興市場の熱狂(1999〜2000年)
- 郵政民営化ブームと新興株(2005年前後)
- リーマンショックと金融危機(2008年)
- アベノミクス相場(2012〜2020)
- 制度改革と個人投資家の復活
- 平成投資ブームの総括
- コロナショックと急速な株高(2020年)
- 米国株人気とSNS投資文化
- インデックス投資と積立投資の定着
- 新NISAによる投資の大衆化(2024年〜)
- 日本株ブームの再燃(2023年以降)
- 令和投資ブームの特徴
- まとめ:令和は投資の「定着期」
はじめに
投資はいつの時代も「ブーム」とともに語られてきました。ある時期には熱狂的に株式や土地に資金が集まり、またある時期には人々が投資から距離を置きました。
この記事では、昭和・平成・令和における日本人の投資ブームの変遷を振り返り、現代の私たちがどのように資産形成と向き合っているのかを考えてみたいと思います。
1. 昭和の投資ブーム(1945〜1989)
戦後復興と投資の始まり(1945〜1950年代)
第二次世界大戦の敗戦後、日本は深刻な経済混乱に見舞われました。
1946年の「新円切り替え」、1949年の「ドッジ・ライン」による緊縮財政で、庶民の生活は苦しく、投資どころではない状況でした。
当時の金融政策は「インフレ抑制」が最優先であり、一般人にとって投資はまだ縁遠いものでした。
しかし1950年代に入ると、朝鮮戦争特需と高度経済成長の波に乗り、製造業を中心に企業が急成長。
これに伴い、株式市場が次第に整備され、証券会社の支店が全国に広がり始めました。
まだ一部の富裕層やビジネスマンに限られましたが、「株を買う」という文化が芽生え始めたのです。
高度経済成長と株式市場の拡大(1960〜70年代)
1960年代は池田勇人首相の「所得倍増計画」が掲げられ、国民の所得が急速に伸びていきました。
東京オリンピック(1964年)開催なども重なり、株式市場は「成長企業に乗るチャンス」として注目を浴びるようになります。
- 鉄鋼、自動車、電機といった輸出産業の成長
- 銀行株や証券株への人気集中
- 初めて株を買うサラリーマンや中流層の登場
この時期、株式は「国民が豊かになる象徴」として位置づけられ、証券投資は少しずつ庶民の世界へ広がりました。
ただし、この段階ではまだ「一部の積極的な人が参加するもの」という色合いが強かったといえます。
財テクと投資熱の高まり(1980年代前半)
1980年代に入ると「財テク(財務テクニック)」という言葉が流行語になりました。
背景には以下の要素がありました。
- 高金利時代:銀行預金だけでも年利5〜6%が期待できた
- 金融商品の多様化:社債、公社債投信、外貨預金など
- 雑誌・テレビが「財テク術」を紹介し、一般家庭にも投資熱が広がった
特に都市部のサラリーマンや主婦が、身近な金融商品で「お金を増やす」ことに関心を持つようになりました。
この流れが、やがて訪れる「バブル期」へとつながっていきます。
バブル経済と史上最大の投資ブーム(1985〜1989)
1985年のプラザ合意を契機に円高が急速に進み、景気が冷え込むのを防ぐため日本銀行は低金利政策を実施しました。
余剰資金が一気に市場へ流れ込み、土地と株式を中心に前例のないバブルが発生しました。
- 株式市場の熱狂:日経平均株価は1989年12月に38,915円を記録。
- 不動産神話:東京の土地価格が異常なまでに上昇し、「日本の土地でアメリカ全土が買える」とまで言われた。
- 個人投資家の大量参入:誰もが株や土地を買い、雑誌や新聞が連日のように投資情報を発信。
この時期の特徴は「全員参加型の投資ブーム」でした。
それまで投資に慎重だった庶民も「やれば儲かる」という空気に押され、資金を市場へ投入。
昭和の投資史は、このバブル絶頂で幕を閉じることになります。
2. 平成の投資ブーム(1990〜2019)
バブル崩壊と「失われた10年」(1990年代前半)
平成の幕開けは、昭和末期の資産バブル崩壊とともに始まりました。
1990年以降、日経平均株価は急落。1989年12月に史上最高値の38,915円をつけた後、わずか数年で半値以下に。
地価も暴落し、「土地神話」は完全に崩壊しました。
銀行は不良債権を抱え、企業はバランスシートの調整に追われ、個人投資家は大きな損失を経験しました。
この時期は「投資は危ないもの」「株はギャンブル」という意識が社会に定着し、多くの個人が市場から撤退。
一方で、長期的に見ればこの時代に証券取引所や金融制度の整備が進み、後の投資文化につながる基盤が築かれていきました。
ITバブルと新興市場の熱狂(1999〜2000年)
1990年代後半、インターネットの普及が進むと、新しい成長株に対する期待が高まりました。
マザーズやジャスダックといった新興市場が相次いで誕生し、ソフトバンクや楽天などIT企業の株が爆発的に上昇。
- 株式雑誌は「次のテンバガー(10倍株)」を特集
- 個人投資家がパソコンで株取引を始める「デイトレ文化」の芽生え
- 「ネット株長者」と呼ばれる人々が話題に
短期間で資産を増やした成功者がメディアに取り上げられ、多くの個人投資家が参入しました。
しかし、2000年のITバブル崩壊で株価は急落し、再び多くの投資家が退場することになります。
郵政民営化ブームと新興株(2005年前後)
2005年、小泉純一郎首相による「郵政民営化」政策が国民的な関心を集めました。
郵政関連銘柄の注目度が高まり、同時期に新興市場でも活発な取引が行われました。
ライブドアなどのベンチャー企業が「時代の寵児」として脚光を浴び、個人投資家も短期売買で盛り上がりました。
しかし2006年のライブドアショックにより市場は急落。新興株投資は一気に冷え込み、再び「投資は危険」という空気が広がりました。
リーマンショックと金融危機(2008年)
2008年9月、米国リーマン・ブラザーズの破綻は世界的金融危機を引き起こしました。
日本株も大暴落し、日経平均株価はわずか1年で1万円を割り込み、7,000円台に突入。
この出来事で多くの個人投資家が大きな損失を抱え、再び市場から退場しました。
平成前半は「投資ブームが起こる→崩壊する→個人が退場」というサイクルが繰り返された時代といえるでしょう。
アベノミクス相場(2012〜2020)
長らく低迷していた日本株を救ったのが、2012年末に誕生した第二次安倍政権の経済政策「アベノミクス」でした。
「三本の矢」と呼ばれる政策(大胆な金融緩和・財政出動・成長戦略)が掲げられ、日本銀行は異次元の金融緩和を実施。
- 円安・株高が急速に進行
- 海外投資家やGPIF(年金基金)が日本株を大量に買い越し
- 日経平均株価は2012年末の8,000円台から、2015年には2万円を突破
株式市場は再び活況を取り戻し、長らく遠ざかっていた個人投資家も少しずつ戻ってきました。
制度改革と個人投資家の復活
アベノミクス期は、単なる株高だけではなく「制度面での投資文化の普及」が大きな特徴でした。
- NISA(2014年〜):少額投資非課税制度が始まり、長期投資の裾野が広がった
- iDeCo(個人型確定拠出年金):将来の年金対策として、若い世代が投資を始める契機に
- 株主還元の強化:企業が積極的に配当や自社株買いを行い、株式保有の魅力が増した
この時期を境に、「投資は一部の人のもの」から「多くの人にとって選択肢のひとつ」へと変化しました。
平成投資ブームの総括
昭和の投資ブームが「バブルの熱狂」で終わったのに対し、平成は「ブームと崩壊を繰り返しながら、制度を通じて投資が定着した」時代でした。
アベノミクスとNISA制度の普及は、令和の「投資の大衆化」につながる大きな橋渡しとなったのです。
3. 令和の投資ブーム(2020〜現在)
コロナショックと急速な株高(2020年)
令和の投資ブームは、2020年の新型コロナウイルス感染拡大から始まりました。
パンデミックによる経済不安から株式市場は急落し、日経平均株価は一時16,000円台まで下落。
しかし、各国政府・中央銀行の大規模な金融緩和と財政出動を背景に、市場は驚異的なスピードで回復しました。
- 米国株(特にGAFAを中心としたハイテク株)が急騰
- 日本株も2021年には30,000円台を回復
- 株価アプリやSNSを通じて若年層の投資家が急増
この時期、投資未経験の20代・30代が米国株や投資信託に参入し、個人投資家の裾野が一気に広がったのです。
米国株人気とSNS投資文化
コロナ禍で特に人気を集めたのは米国株でした。
S&P500やNASDAQ100に連動する投資信託・ETFは「右肩上がりで成長するアメリカ」に乗る投資法として支持され、TwitterやYouTubeで発信する個人投資家が急増しました。
- **「積立NISAで米国株投資」**が定番に
- インフルエンサー投資家が情報発信し、若年層に拡散
- 投資ブームがSNSコミュニティ化し、孤独ではなく仲間と学びながら投資する時代に
この「SNS投資文化」は、昭和や平成には見られなかった令和ならではの現象です。
インデックス投資と積立投資の定着
令和に入り、投資は「一攫千金のための手段」から「資産形成のための習慣」へとシフトしました。
積立NISAやiDeCoを通じて、毎月の積立投資をするのが当たり前になりつつあります。
従来の投資ブームが「盛り上がって崩壊する」一過性のものだったのに対し、令和の投資ブームは長期投資が制度に支えられている点で異なります。
また、金融リテラシー教育の強化も進み、2022年度から高校家庭科で「資産形成」が必修となったことも大きな変化です。
新NISAによる投資の大衆化(2024年〜)
2024年1月から新しいNISA制度がスタートしました。
- 非課税枠が大幅拡大(生涯1,800万円まで投資可能)
- 恒久化により「期限切れで売らなければならない」制約が消滅
- 成長投資枠で個別株にも幅広く投資できる
この制度改正は、まさに投資ブームを後押しするもので、多くのメディアが「国民的投資時代の幕開け」と報じました。
特に20代・30代の若年層が積極的に参加しており、投資は一部の富裕層や投資好きの趣味ではなく、社会人なら誰もが関わるライフプランの一部となりつつあります。
日本株ブームの再燃(2023年以降)
さらに、2023年以降は円安やインバウンド需要、企業の自社株買いを背景に日本株が再評価されました。
海外投資家の資金流入も続き、日経平均株価は34年ぶりにバブル期の高値を更新。
- 海外投資家が主導する日本株買い
- 個人投資家も「日本株は終わった」という固定観念を見直す動き
- 高配当株投資や日本株ETFの人気急上昇
かつて平成初期に崩壊した日本株への信頼が、令和になって再び回復しつつあるのです。
令和投資ブームの特徴
昭和や平成の投資ブームが「熱狂と崩壊」を繰り返したのに対し、令和の投資ブームは以下の点で異なります。
- 制度に支えられている(新NISA・iDeCo)
- SNSによる情報拡散とコミュニティ化
- 投資が教育と生活習慣に組み込まれた
- 日本株の再評価が同時進行している
投資はもはや一時的な流行ではなく、生活の中に根づいた「資産形成の習慣」として浸透しています。
まとめ:令和は投資の「定着期」
令和の投資ブームは、昭和の熱狂、平成の挫折を経て、ようやく投資が文化として定着した時代だといえるでしょう。
ブームは終わるものですが、制度と習慣に支えられた令和の投資は、過去とは違う持続力を持っています。
全体のまとめ
昭和・平成・令和を通じて、日本人と投資の関わりは大きく変化してきました。
- 昭和は高度経済成長とともに株式市場が広がり、バブル経済期に「国民的投資ブーム」の熱狂が最高潮に達しました。しかしその反動で崩壊を経験し、「投資=危険」という印象を残しました。
- 平成は崩壊から始まり、ITバブルや郵政民営化、リーマンショックといった波乱を繰り返しながらも、最終的にアベノミクスとNISA制度により「投資を生活に取り入れる土台」が整った時代でした。
- 令和はその基盤の上に、コロナ禍を契機に投資が一気に大衆化し、SNSや金融教育を通じて若い世代にまで浸透。新NISAやiDeCoが制度的に支え、投資が「一時的なブーム」ではなく「生活習慣」として定着しつつあります。
つまり日本の投資史は、
「昭和の熱狂」→「平成の挫折と制度整備」→「令和の定着」
という流れで整理できます。
過去のブームの教訓は、常に「熱狂は長続きせず、冷静な長期投資が重要」ということを示しています。
現代を生きる私たちは、昭和や平成の失敗を学びつつ、令和の制度と環境を活かして「持続可能な資産形成」を進めていく必要があります。
📚 引用・参考文献
本記事を執筆するにあたり、以下の公開情報・資料を参照しました。
- 日本証券業協会『証券投資の歩み』https://www.jsda.or.jp/about/outline/history.html
- 日本銀行『戦後日本の金融史』https://www.boj.or.jp/about/activities/act/fin_sys/
- 財務省『戦後経済の歩み』https://www.mof.go.jp/
- 内閣府『経済白書』歴代版https://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp.html
- 東京証券取引所(JPX)「統計・株価情報」https://www.jpx.co.jp/
- 野村総合研究所『日本人の投資行動の変化』調査レポート
- 日本経済新聞・日経電子版(バブル期、ITバブル期、アベノミクス、新NISA関連記事)
- Bloomberg, Morningstar 各社による日本株市場レポート

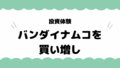
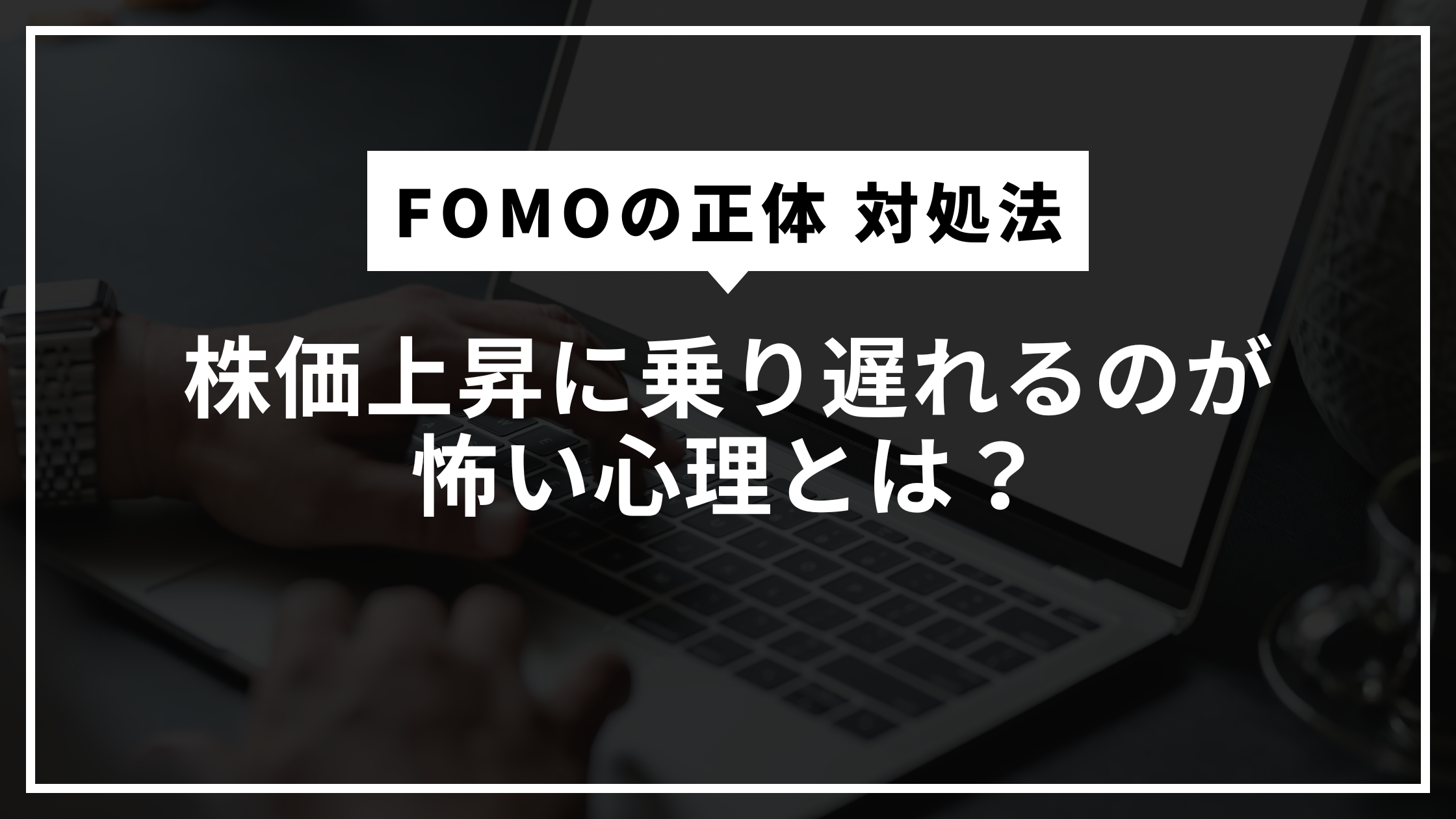
コメント