はじめに
金曜ロードショウで放送される『火垂るの墓』は、1945年(昭和20年)、太平洋戦争末期の神戸を舞台としています。
主人公たちの悲劇的な運命は物語として強い印象を残しますが、その背景には、当時の日本経済・株式市場・企業構造の劇的な変化があります。
本記事では、戦時下から終戦直後にかけての日本と世界の経済史を、
- 株式市場の動き
- 企業ランキング
- 当時の暮らしと物価といった切り口で振り返ります。
1. 戦争が経済を変えた
1-1 軍需優先経済への転換
1941年の日米開戦以降、日本の経済は完全に軍需優先へと転換しました。
民間の生活物資や消費財の生産は抑えられ、鉄鋼、造船、航空機、軍服、燃料などの生産が最優先されます。
- 綿糸・毛糸 → 軍服・毛布に回される
- 食用油 → 潤滑油や軍用燃料に転用
- 自転車や時計 → 製造制限対象
結果として、生活必需品は極端に不足しました。
1-2 戦時インフレ
物資不足の一方で、政府は戦費調達のために国債発行と紙幣増刷を行い、インフレが進行しました。
公定価格と実勢(闇市)価格の乖離は年々拡大します。
| 年 | 米(公定価格・1升) | 米(闇市価格・1升) |
|---|---|---|
| 1941年 | 約30銭 | 約35銭 |
| 1945年 | 約1円 | 20円以上 |
※1升=約1.5kg
1-3 配給制度と闇市
生活物資は配給制となり、国民は「配給切符」を持って受け取りますが、量・質ともに不足。
成人1人あたり1日米2合(約300g)程度まで減少し、代用食が主流となります。
不足分は闇市で補うほかなく、農村から持ち込まれる米や芋、魚が高額で取引されました。
闇市は生活の命綱であり、同時に戦時インフレの象徴でもありました。
2. 戦時下の日本株式市場
2-1 統制下の市場
昭和15年(1940年)以降、株式市場は自由な取引の場ではなく、戦費調達と国策企業支援のための制度へと変化しました。
- 東京株式取引所は「日本証券取引所」へ統合(1943年)
- 売買制限により取引量は戦前の1/10以下
- 株価は事実上の固定化に近い状態
2-2 株価推移(推計)
| 年 | 日経平均換算値 | 備考 |
|---|---|---|
| 1939年 | 約150円 | 日中戦争長期化 |
| 1941年 | 約120円 | 太平洋戦争開戦 |
| 1944年 | 約90円 | 戦況悪化 |
| 1945年8月 | 約85円 | 終戦直前 |
| 1945年12月 | 約60円 | 終戦後の混乱 |
※当時の東証平均株価を現在の指数換算で推計。
2-3 金融政策と株式
- 大量の戦時国債発行
- 日銀による引き受けで市中に紙幣供給
- 株式は現金化しにくく、金・不動産・物資へ資金流出
3. 終戦直後の市場
1945年8月の終戦後、株式市場は休場し、同年12月に再開。
しかし企業業績の悪化とインフレ加速で株価は低迷します。
1946年には新円切替と預金封鎖が実施され、資金流動性が大きく制限されましたが、
インフレヘッジとしての株式需要も少しずつ回復し、1948年頃から上昇基調へ。
4. 1940年代日本の主要企業ランキング(資本金ベース)
戦時下の大企業は、ほぼ軍需・輸送・基幹産業に集中していました。
| 順位 | 企業名(当時) | 業種 | 資本金(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵船 | 海運 | 約2億円 | 世界有数の船隊規模 |
| 2 | 三菱重工業 | 重工業 | 約1.8億円 | 戦艦・航空機生産 |
| 3 | 三井物産 | 商社 | 約1.7億円 | 資源・食料輸入 |
| 4 | 南満州鉄道 | 鉄道・商社 | 約1.6億円 | 満州経営の中枢 |
| 5 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | 約1.4億円 | 軍需用鋼材供給 |
| 6 | 日本製鐵 | 鉄鋼 | 約1.3億円 | 現・日本製鉄の前身 |
| 7 | 大阪商船(後に日本郵船と統合) | 海運 | 約1.2億円 | 輸送船団運営 |
| 8 | 東京電燈 | 電力 | 約1.0億円 | 戦後東京電力へ |
| 9 | 東洋紡績 | 繊維 | 約0.9億円 | 軍服用生地供給 |
| 10 | 大日本帝国製糖 | 食品 | 約0.85億円 | 軍需用砂糖供給 |
※当時の1億円は現在の数千億円に相当。
5. 世界の主要企業ランキング(売上・影響力ベース)
戦勝国アメリカでは、製造業・石油・鉄鋼が世界経済を牽引しました。
| 順位 | 企業名 | 国 | 業種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェネラル・モーターズ(GM) | 米 | 自動車 | 世界最大の自動車メーカー |
| 2 | U.S.スチール | 米 | 鉄鋼 | 世界最大の製鉄会社 |
| 3 | スタンダード・オイル(NJ) | 米 | 石油 | 後のエクソンモービル |
| 4 | デュポン | 米 | 化学 | ナイロン・火薬生産 |
| 5 | フォード・モーター | 米 | 自動車 | 軍用車両大量生産 |
| 6 | GE(ゼネラル・エレクトリック) | 米 | 電機 | 家電・発電機生産 |
| 7 | シェル石油 | 英蘭 | 石油 | 植民地資源を供給 |
| 8 | IBM | 米 | 機械 | パンチカード集計機で軍需支援 |
| 9 | ボーイング | 米 | 航空機 | 爆撃機・輸送機生産 |
| 10 | コカ・コーラ | 米 | 飲料 | 戦地供給でブランド拡大 |
6. 世界株式市場の推移
米国市場(NYダウ)
| 年 | NYダウ(年末) | 備考 |
|---|---|---|
| 1939年 | 約150ドル | 欧州戦争開始 |
| 1941年 | 約120ドル | 真珠湾攻撃 |
| 1942年 | 約92ドル | 戦時の底値 |
| 1945年 | 約192ドル | 戦後上昇期開始 |
欧州市場
- 英国は戦時も市場継続
- ドイツ市場は戦況悪化で機能停止
- 戦後は復興資金と米資本の流入で再建
7. 為替と国際経済
日本は戦前レート1ドル=4.2675円を維持していましたが、戦後経済は混乱し、実質的価値は大きく低下。
海外との取引はほぼ停止し、外貨不足が長期化しました。
まとめ
『火垂るの墓』の背景にある1940年代の経済史は、
- 日本では株式市場が国策の一部となり、投資自由度が消失
- 大企業は軍需・輸送・基幹産業に集中
- 米国は戦争を契機に経済拡大、世界経済で優位を確立という構造でした。
物語の感動の裏には、このような経済と社会の激変があったことも忘れてはなりません。
参考文献
- 日本銀行金融研究所『戦時経済下の日本金融史』
- 大阪証券取引所編『日本株式市場史』
- 国立国会図書館デジタルコレクション「戦時物価統制資料」
- 岩波新書『昭和史(半藤一利)』
- U.S. Bureau of Economic Analysis “Historical GDP and Corporate Rankings”
- New York Stock Exchange Historical Data Archives
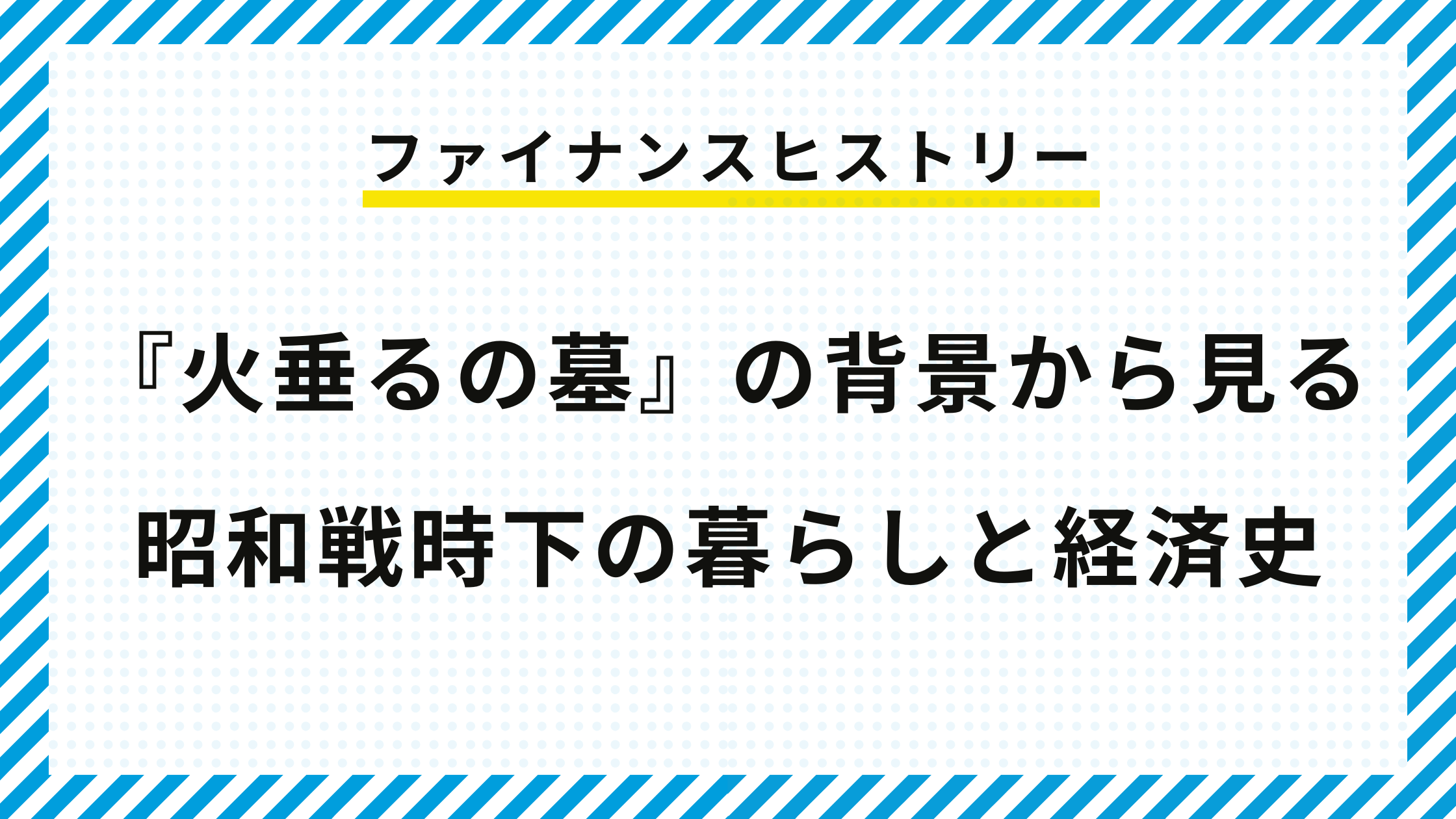
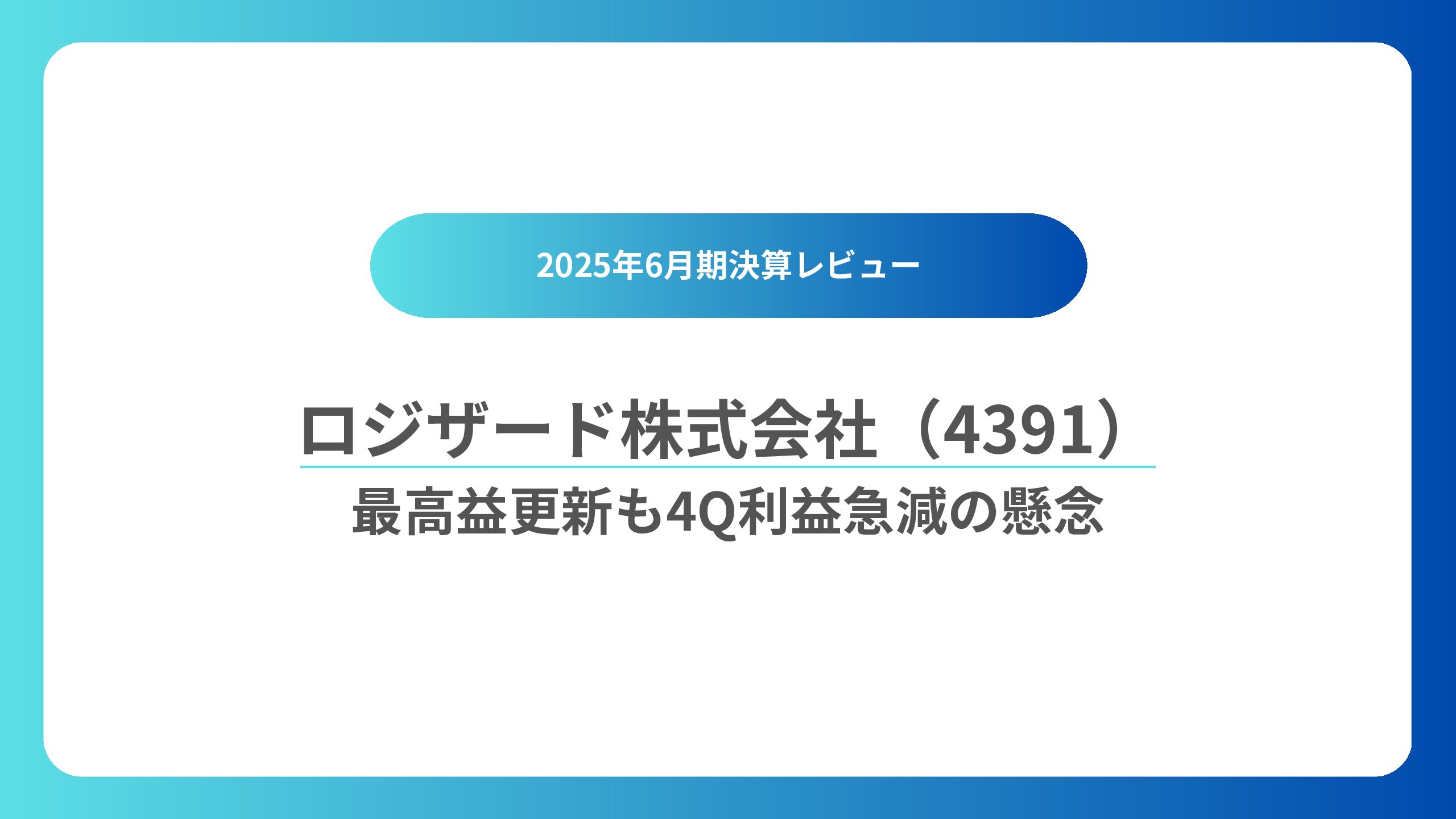
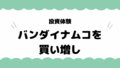
コメント